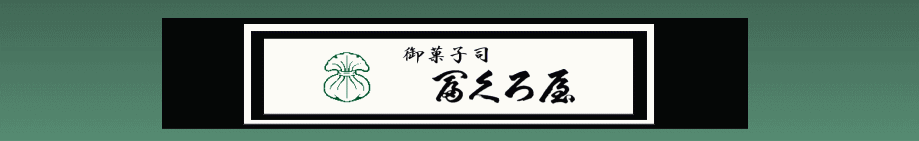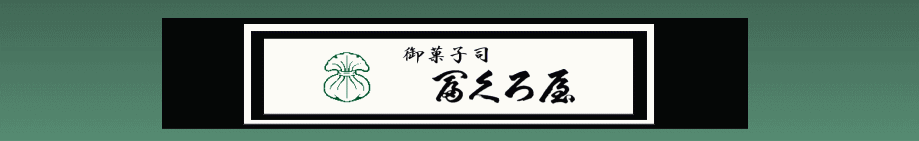|
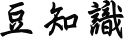 File1 〜File10 File1 〜File10 |
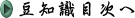 |
|
|
|
|
file10 着物.の種類
着物は知識よりセンスです。
−「着物の悦び」林真理子 光文社ー
彼女のように、着物を愛し豊富な知識がある方ならではの言葉です。
しかし、やはり基本は知っておきたいです。
|
カジュアル
普段着の要素が強いです。
それだけに、着物と帯
小物などで楽しむことが
できます。
(例)
お茶のお稽古・お茶会
観劇・お食事・ショッピング
花火大会・初詣
|
 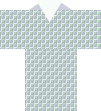
(浴衣) (織り) |
カジュアル〜中間
小紋・色無地は一番活
用の範囲が広いとされ
ています。
(例)
お茶のお稽古・お茶会
観劇・お食事
卒業式の袴に合わせる
|
 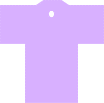
(小紋) (色無地)後ろ |
中間〜フォーマル
正式な場所や少し改まっ
た場所のお出かけに。
(例)
お茶会・結婚披露宴
観劇
|
  
(付け下げ) (訪問着) (色留袖)後ろ |
フォーマル
第一.の礼装
(例)
結婚式・成人式 |
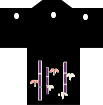 
(留袖)後ろ (振袖) |
|
着物のルールは日々変わっていっているようです。
昨今は、アンティーク着物が流行ったりしています。
夏に浴衣を着るように、普段着の一つに加えてみませんか。
おばあ様やおかあ様の箪笥にきっと眠っています。
|
|
file9 床の間と書画
茶の湯は、実に多岐にわたる要素によって構成されています。奥深いものです。
この機会に.、広く、浅くではありますが、ご一緒に勉強してみませんか。
茶道以外でも、きっと役立つと思います。「知る」ことは案外楽しいです。
まず、床の間(座敷の正面上座に床を一段高くした場所)に掛けられた、
掛け軸(書画)についてです。
茶の湯の掛物としての主な書画は、大きく分けると三種類です。
(1) 絵画 ・中国の絵画
・日本の絵画 |
 |
* 1
(2) 書 ・墨蹟 ・一行書
・色紙 ・短冊 |
 |
* 2
(3) 画賛物
|
 |
「掛物.ほど第一の道具はなし.」と千利休の言葉があります。 −[南方録]ー
書画は茶席の主題とされるほどだそうです。
ぼくせき
* 1 墨蹟・・・・・・一般では筆蹟のことですが、茶道では禅僧の書のことです。
がさんもの
* 2 画賛物・・・・画上に、筆者以外の人物が詩歌や感懐などを書き付けているもの。
画も字も同一人物が記したものは自画賛といいます。
ー 参考文献 ー 「茶道入門」田中仙翁 三省堂
|
|
file8 真・行・草
しん ぎょう そう
真 ・ 行 ・ 草 とは、元々は書道の漢字書体からのようです。
真 端正な楷書で正格
行 真と草の中間
草 型にとらわれない自由で風雅な形
他にも、茶道・華道・庭園・絵画など伝統のある物にみられます。
実は、干菓子にもあります。
真 落雁などの打ち物
行 寒氷や錦玉
草 有平糖
干菓子を二種盛りにする場合は、真のものを向こう側にします。
干菓子の数は、お客様の数より少し余分目がよいようです。
* ご家庭でも、景色を楽しみながらお使い下さい。
コーヒや紅茶に添えるのも一興です。
|
 |
|
|
file7 茶花と花入れ
茶花は感覚でいれるもので、いけ花のように花型があるわけではない。
ぱっと心が打たれる、心でいけるのがよい茶花である。
[ 山藤宗山 ]
花入に対する花の角度
真の花入 まっすぐにいれる。
(胡銅や青磁)
行や草の花入 やや傾けて入れる事が多い。
口の広い花入にいれる場合は、木を渡すか中筒を。
とは言うものの中々難しいです。
私どもも、花を店頭に置いてあると、風などで形が定まりません。
ちょっと、簡略てす。
|

(針金を、花入の大きさに合わせて丸めます。)
|

(花入にいれます。)
|
*注 繊細な花瓶には使わないでください。
花瓶を傷めます。お気を付け下さい。
|
|
file6 和菓子の歴史
縄文時代 最初、木や草の実などの果実が味わわれていました。
稲作のつたわる縄文時代晩期、保存や持ち運びのよい、
団子や餅の原型が見いだせます。
平安時代 遣唐使らにより「唐菓子(からくだもの)」や、
米や麦の粉の生地を形どり、油で揚げた加工品などがありました。
鎌倉時代 禅宗とともに伝わった菓子が現れました。
これらは、点心で現代のように彩りのある甘味の多い菓子では
ありませんでした。
室町時代 次第に工夫され、小豆あんの塩味の饅頭が出来始めます。
羊羹や饅頭の原型が現れました。
ザビエルの来朝以降、南蛮の珍しい食品が我が国に持ち込まれます。
カステラ・パン・ビスケット・金平糖・有平糖などです。
江戸時代 江戸時代中頃、茶の湯の発展とともに茶人の美意識によって
菓子も具現化され始めました。
明治時代 洋菓子に対して、和菓子言う言葉が一般の国語辞典に掲載されました。
|
|
 file5 菓子箱と風呂敷 file5 菓子箱と風呂敷
菓子箱などを風呂敷で包む時、大きく分けると3種類あります。
平包み 風呂敷を結ばないで包みます。
一つ結び包み 一カ所だけを結ぶ包み方です。
比較的軽い物を包みます。
二つ結び包み 十字に二カ所を結ぶ包み方です。
重たい物を包みます。
詳しい包み方はこちらから↓
http://homepage2.nifty.com/futava/furosiki/method/meth.htm
風呂敷は、日本の良き生活文化です。

(一つ結び包み)
|
|
 file4 着物と季節 file4 着物と季節
着物には、季節によって「決まりごと」があります。
ゆかた
7〜8月 薄い夏物(薄くて透ける素材)・浴衣
ひとえ
6月・9月 単衣(裏地がついていない着物)
あわせ
それ以外の月 袷(裏地のついた着物)
前後1週間程はどちらにしても良いそうです。
最近、若い方も着物を楽しんでいらっしゃいます。
春と秋は、お茶会の季節です。着物でお出かけしませんか。
|
|
ile3 芋名月と豆名月
旧暦八月十五日夜の満月を、「中秋の名月」(芋名月)と言います。
十五夜に、お月さまに芒(すすき)を飾って月見団子・子芋・枝豆などを三宝に盛りました。
子芋は、皮のまま蒸した衣被(きぬかつき)を三宝に盛ってお供える風習がありました。
天の恵みで出来た作物に感謝し、月に捧げると言う意味です。
この風習から「芋名月」と言われるようになりました。
ちなみに、旧暦九月十三夜の月は「豆名月」と言われています。
収穫の時期の違いからのようです。
*地方によって呼び名に違いはあるようです。

|
|
file2 重陽の節句と着せ綿
昔の中国では、陽の数字(奇数)の重なりを避けるため、避邪の行事が行われていました。
1月7日・・・七草の節句
(1月だけは1日を別格とします)
3月3日・・・桃の節句(ひな祭り)
5月5日・・・菖蒲の節句(端午の節句)
7月7日・・・笹の節句(たなばた)
9月9日・・・菊の節句(重陽の節句)
こちらが五節句と言われています。
旧暦九月九日(2010/10/16)は重陽の節句です。
重陽の前夜、菊花の上に綿を置き、夜露・朝露を含んだものを、
「着せ綿」と呼び、この綿で身を拭うと、肌つややかに老いも去るとされました。
菊を象った練り物の上に、白いそぼろを綿に見立ててかけてある。
「着せ綿」といわれるこのお菓子は、菊にまつわる伝説にあやかり出来ました。
長寿を祈ってこのお菓子でお茶を喫するのも一興です
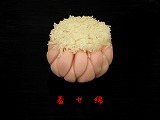
|
|
file1 おはぎとぼた餅
おはぎとぼた餅は、同じものなのだと言う説が一般的です。
つまり、食べる時期の問題なのです。
ぼた餅は、牡丹の花咲く春のお彼岸に食べるから「牡丹餅」と言われています。
おはぎは、萩の花咲く秋のお彼岸に食べるから「お萩」と言われています。
春の彼岸は農作業が始まる時期で、秋の彼岸は収穫の時期です。
この時期、小豆の赤は災害が身に降りかからないように、魔除けの意味があったので、
おはぎ(ぼた餅)を食べる習慣ができたようです。
誠に申し訳ございません。当店では、おはぎ(ぼた餅)は扱っておりません。
ただ毎年、餡をお買い求めになるお客様がいらっしゃいます。
ご家庭で、上質の餡を使っておはぎ(ぼた餅)を作ってみませんか。
|